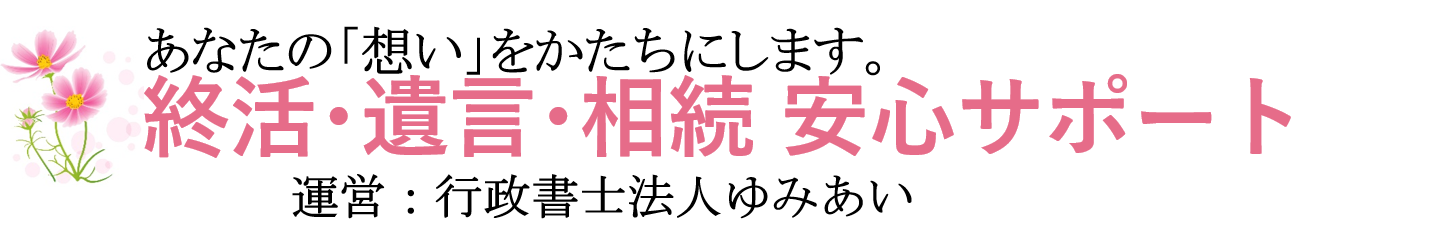お世話になった人に財産を残したい方の遺言書

生前家族のように親身になって接してくれた人、温かく見守りサポートしてくれた人に自分の死後、財産を残したいと思われる方もいらっしゃいますよね。

財産を受け取る方が相続人とのトラブルに巻き込まれたりしないように、また自分が財産を受け取ってもいいのかと困惑しないために受け取る方の気持ちを考え配慮した遺言書を残せるといいですよね。
ここではそんな「お世話になった人に財産を残したい方の遺言書」ということで注意すべきポイントを5つお伝えいたします。
1.遺留分(いりゅうぶん)に注意する
たとえ「全財産をお世話になった友人のAさんに遺贈する」という内容の遺言書を書いたとしても必ずしも全財産がAさんに遺贈されるとは限りません。(遺言により相続人以外の人に財産をゆずることを遺贈(いぞう)といいます。)
法律上法定相続人には「遺留分」(いりゅうぶん)という被相続人の相続財産のうち最低限度受け取れる財産として法律で保証されているものがあります。(※遺留分の割合は法定相続分の1/2です。)
なので遺言書を書いて準備しておいたとしても、残念ながら必ずしも全財産が思い通りに遺贈できるとは限らないのです。
しかし遺留分は相続人により「請求」されないと効力は発生しません。
なので、できるだけ遺留分を請求されないよう生前に対策しておくことが重要です。
しかし遺留分を侵害していれば、受遺者は相続人により「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
受遺者にこういった面倒をかけたくないのであれば、遺留分を侵害しない内容の遺言を検討するようにしましょう。
遺産を換価処分して金銭で遺贈する内容の清算型遺言にしておくと、相続人や受遺者に分配しやすいです)

2.遺贈(いぞう)の理由を明記する
もし法定相続人により少しでも請求されるであろう可能性があり、心配な方は遺言書内に「遺贈の理由を明記する」ことによって法定相続人も遺言者の気持ちを理解することができ、遺留分の請求をしない可能性が期待できます。

想いや理由を書くことによって、法定相続人による遺留分の請求がされにくくなるという可能性があります。
そして遺贈の理由を明記するもう一つの理由が、遺贈を受ける人がある日突然、財産をあげると言われても受け取っていいものかと困惑する人もいるかと思います。相続人のことを考え心配や不安になる方もいるかと思います。
人の気持ちは人の気持ちで動くことも大いにあります。
遺言者の「想い」を明記しておくことは相続財産を受け取る人や残された相続人の「心」や「想い」にとって、とても大切なことです。

3.遺言執行者を指定しておく
お世話になった人に財産を譲る遺言書では、遺言書の中で遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定しておきましょう。
預貯金の解約や不動産の名義変更では様々な手続が発生します。
そしてたくさんの書類を準備しなければなりません。
被相続人の戸籍謄本なども必要であったり、相続人でない受遺者(遺産を受取る人)が相続人の協力なしにそれらを取得することは難しいです。
ですので受遺者が単独で不動産の登記名義人の変更や預貯金の解約・払戻し手続きををするのはとても難しいことです。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとその遺言執行者は単独で預貯金の解約手続きや不動産の名義変更を行うことができます。
受遺者(遺産を受取る人)が遺言執行者となることもできますが、相続人がいる場合、相続人とやり取りをしなければいけない事もあるので士業など遺言相続の専門家を指定しておいた方が遺産を受取る人の負担が少なく安心です。

・遺言執行者に就任したことを相続人に通知する
・戸籍謄本などを収集し、相続人調査を行う
・相続財産を調査する
・財産目録を作成する
・受遺者に対して、遺贈を受けるかどうかの意思確認をする
・預貯金の解約・払戻し手続きを行う
・分配する財産については売却して換価手続きを行う
・不動産の所有権移転登記を行う
・有価証券等の財産の名義変更手続きを行う
・相続人と受遺者全員に完了報告を行う
4.相手が特定できるように書く
お世話になった人や特定の人に財産を譲る場合は、その人が特定できるよう
・氏名
・住所
・生年月日
を明記します。
また財産も特定できるように明記します。
遺贈する相手がどこかの公益法人や医療団体などの場合、個人の不動産の遺贈をそのまま受けるとかえって面倒になることがあります。
「不動産は換金処分して遺贈する」などと記載しておくのがいいでしょう。
個人や法人格を持っていない団体の場合は原則として相続財産額により相続税が加算されます。
そして株式会社などの場合は相続税は課税されなくても法人税は課税されます。
団体等が公益的な事業を行っている場合には、非課税になることがあります。
なお遺贈先が税金を負担しないですむためには、
・公益性が高い事業であること
・遺贈された財産を事業のために使うこと
・遺贈されてから2年以内に使うこと
・特定の者とその家族、親族により運営される公益事業ではないこと
などの条件があります。
遺贈寄付する時は事前に寄付先に寄付を受け付けているのか、その方法など確認しておくと安心です。
なお、遺贈する相手が遺言者の死亡時にすでに亡くなっていたり、遺贈先の団体や法人がすでに解散をしていた場合はその内容は無効となります。
よって、予備的にそういったことに備えて別の財産の帰属先(遺贈先)も検討しておきます。(これを予備的遺言といいます)
受遺者が遺贈を放棄し、また予備的遺言をしておいてもその予備的遺言の受遺者も放棄する可能性があります。
そのような場合は、その財産に関しては相続人に帰属します。
5.遺贈の方法に注意する
遺贈の種類には
・「包括遺贈」(ほうかついぞう)
・「特定遺贈」(とくていいぞう)
の2種類があります。
「包括遺贈」とは財産の全部または一定の割合を指定する遺贈です。
「特定遺贈」とは○○銀行○○支店口座番号○○○○○○など特定して行われる遺贈です。
この包括遺贈と特定遺贈には、その効果に違いがいくつかあります。
まず、包括遺贈の場合、遺贈を受ける人には「相続人と同一の権利義務」があります。
よって遺言者に借金などの債務がある場合、その債務も承継することになります。
遺贈をしたい人に借金などのマイナス財産の負担を負わせたくない場合、特定遺贈で財産を特定した形で遺贈するようにしましょう。
また包括遺贈では相続放棄をするのに家庭裁判所へ申述する必要があり、放棄手続きは煩雑なので受遺者の負担となります。
一方特定遺贈では家庭裁判所に申述する必要はなく、「その意思を表示するだけで足りる」とされています。
まとめ
お世話になった方になんらかの形で恩返しをしたり、気持ちを伝えれると素敵ですよね。
大事に思う相手だからこそ、相手が困らないように、また滞りなく遺言の内容が実現できるように専門家のサポートを受けきちんとした遺言書を作成されることをおすすめします。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。