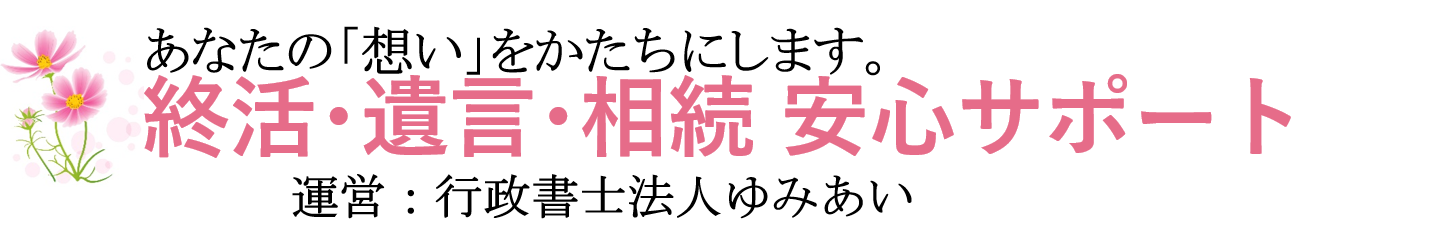子の相続分に差をつける遺言書 / 作成時のポイントと注意点
 老後、自分の面倒をみてくれた子供や家業をついでくれる子供に他の兄弟よりも多く財産を残してあげたいと思うこともありますよね。
老後、自分の面倒をみてくれた子供や家業をついでくれる子供に他の兄弟よりも多く財産を残してあげたいと思うこともありますよね。


そのような内容の遺言書を作成する時に気をつけるべきポイントと注意点をお伝えします。
1.遺留分に注意する
遺留分(いりゅうぶん)とは法定相続人が最低限度受け取れる相続分として法律で決まっています。
なのでたとえ遺言書に全財産を遺贈するとあってもこの法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
基本的には自分が相続できる法定相続分の1/2もしくは1/3になりますが、遺留分の割合はどの相続人がいるのかによって変わってきます。
 たとえば、子どもが長男の太郎と長女の花子の二人だったとします。
たとえば、子どもが長男の太郎と長女の花子の二人だったとします。
長女の花子は自分が嫁いだあとも度々実家へ戻り食事の世話や掃除などしてくれました。
生前何もできなかったこともあり、自分が亡くなった後は少しの預貯金と不動産は長女花子に譲りたいと思います。
この時長男の太郎には遺留分の請求権があるのでそのことをふまえながら遺言書を作成します。
方法としては、
①付言を残し長男の理解を得る
②遺留分額の金銭を太郎に相続させる
このように遺留分に配慮した遺言書を作成するようにしましょう。
2.公正証書で作成する
例えば長男に全財産を相続させる、次男には何も相続させないという内容の遺言書を書くと、「相続争い」が起が起こる可能性もあります。
このような相続争いが起きた時の争点として「この遺言書は本当に本人の意思によって書かれたものなのか、本心なのか」という点が争われることがあります。
例えば自筆証書遺言で作成した場合、本当にこれが本人の直筆なのかという点が争われることがあります。
本人の意思によって書かれたものなのか、この点は認知症になり判断能力が低下していたなどと本人の意思能力や遺言能力が疑われ争いとなることがあります。
こういった不要な争いを避けるため「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。
公正証書遺言は公証役場で公証人に本人が内容を伝えて作成するので本人確認が行われているのと、内容も本人の意思であること、意思能力、遺言能力があることが公証人や証人二人の立会人によって担保されています。
本心なのかという点もわざわざ公証役場に出向いて作成し、証人二人も立てていることから本心だと推測できます。
そした、遺言書内に「付言」という形でメッセージを残しておくと残された相続人の心に届き、遺言の内容を受入れられやすくなるでしょう。
3.寄与(療養看護や家業をサポートした)
長年被相続人の療養看護をしたり、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に相続分以上の財産を取得させるため、寄与分という制度があります。
また長男の嫁が療養看護をしていた場合「特別の寄与」が認められる場合もあります。
これは被相続人が亡くなったあとに「寄与をした者」と「相続人」との協議により決まります。
寄与が認められるためにはある一定の要件を満たす必要があり、話し合いで主張するには証拠書類などが必要な場合もあります。
遺言書を作成し、寄与分がある場合は遺留分の請求に備えて生前に対策をしておいた方がいいでしょう。
もし話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停や審判の申し立てをします。
4.相続人の廃除
生前に虐待や重大な侮辱を受けたり、著しい非行行為があった場合、その相続人を遺言書内で廃除することができます。
廃除は遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てを行います。
なお、遺言者が生前におこなった廃除を遺言書で取り消すこともできます。
遺言書内で相続人の廃除を希望する場合、遺言者が「この人物を相続廃除したい」と望んでいたという意思と具体的な理由を遺しておく必要があります。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。