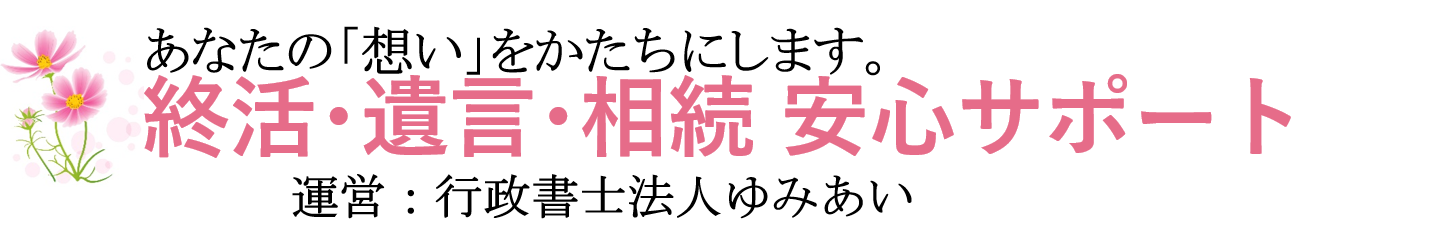財産を寄付したい方の遺言書 / 寄付先の選び方・注意点

最近では生涯未婚などによりおひとり様の数も増加しています。
また配偶者が先に亡くなり、子供がいない方など相続人がいらっしゃらない方もおられます。
相続人がいないとその方の財産は国庫に帰属します。
しかし、遺言書を書いておくことで自分の残された財産を特定の人に遺贈したり、公益事業を行っている団体や医療・福祉などの活動を行っている団体などに寄付することができます。
自分の死後、財産をどこかに寄付したいと思った時その選び方と注意点をお伝えします。

1.寄付先の選び方
NPO法人や公益法人、医療支援や災害復興支援団体などさまざまな寄付先があります。
まずご自身がどういった活動をしている団体に寄付したいのか考えます。

ホームページや団体のパンフレットで確認することができます。
寄付先によっては不動産などの現物を受け入れているところと、そうでないところがあるので事前に確認しておきましょう。
また寄付は団体などではなく個人にもすることができます。
しかし個人や法人格を持っていない団体の場合は原則として法人税が加算されます。
ただし、その団体等が公益的な事業を行っている場合には、非課税になることがあります。
株式会社などの場合は相続税は課税されなくても法人税は課税されます。
寄付遺贈する時は事前に寄付先に意思を伝え確認しておくと安心です。
2.寄付する時の注意点
①遺留分に注意する
もし法定相続人がいる場合、全財産をどこかの団体などに寄付すると遺言書に書くと、その団体が相続人により遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受ける可能性があります。
遺留分とは法定相続人が最低限度受け取れる相続分として法律で決まっているのでたとえ遺言書に全財産を遺贈するとあってもこの法定相続人の遺留分を侵害することはできません。
自分には相続人がいないので大丈夫と思っていても実際には戸籍上隠れた相続人がいたなんてこともあります。(再婚、養子縁組や認知などで戸籍上自分には知らされていない相続人がいることがあります)
なので遺言書を作成する時は専門家に依頼するなどして一度相続人調査をしておいた方が安心です。
一般的に遺言書作成と合わせて士業事務所などで調査してもらうことができますが、相続人調査単体でも3~5万円ぐらいで調査してもらうことができます。
そして相続人の調査が終わり、法定相続人がいることが確定するとその法定相続人に配慮した遺言内容を検討します。
もし法定相続人がいなければ全額寄付することができます。
なお遺留分は法定相続人全員に認められているわけではなく、兄弟姉妹には認められていません。


②遺言執行者を指定しておく
財産を受け取る人や団体がその寄付、財産を受け取る遺言内容の実現をすることもできますが、受け取る側からすると様々な手続きが発生し負担になることがあります。
金融機関では預貯金の解約手続きが必要になりますし、財産に不動産が含まれていた場合、家屋をそのまま貰っても困る団体も多いかと思うので換金処分をしてから受け取れる方がいいでしょう。
それらの手続きには専門的な手続きを要するため、遺言書の中で士業などの「遺言執行者」を指定し、財産を受け取る人の手を煩わせないようにしておく方がいいでしょう。
遺言執行者は遺言書の中で指定します。
③書き方は「特定遺贈」にする
遺言書で財産を寄付する時の指定方法として「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
包括遺贈とは特定の人に財産の全部とか一部とか割合を指定して遺贈する方法です。(何%とが1/2とか)
また包括遺贈の場合、実質的には相続人と同じ権利義務を負うことになります。
もし被相続人に借金などのマイナス財産があればそれも引き継ぐことになります。
そして遺贈は放棄することができますが、特定遺贈の放棄は受贈するとされている者がいつでも放棄をすることができるのにに対し、包括遺贈の場合家庭裁判所に対する包括遺贈放棄の申述が必要です。
包括遺贈放棄の申述は、包括遺贈があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
つぎに、特定遺贈とは「○○県○○市○○町○番○-○」の土地をAに遺贈すると財産を特定して遺贈する方法になります。
このように特定の財産を指定して遺贈しておくことで、受贈者(財産を受け取る人)はマイナスの財産を受け取るというリスクがなくなります。

3.寄付の放棄
もし自分が特定の団体に寄付するという内容の遺言書を残していたとしても、その団体はその寄付を受け取るかどうか選択することができます。
包括遺贈の場合3か月以内に家庭裁判所に包括遺贈放棄の申述をします。
特定遺贈の場合法律上、期限の定めはありません。
しかしもし他に相続人がいた場合、その特定遺贈を受けるのか放棄するのかいつまでもはっきりとしないと相続人は困ってしまいます。
受遺者(財産を遺贈される人)が遺贈を放棄すると相続人の受ける財産が変わってくるからです。
そこで、相続人などの利害関係人は受遺者に対してその特定遺贈を承認するのか放棄するのか確認の催告を行うことができます。
なおこの催告を行っても決められた期間内に受遺者が解答しない場合、その特定遺贈は承認したものと見なされます。

①寄付先を決める
②遺留分に注意する
③遺言執行者を指定しておく
④遺言書は「特定遺贈」で書く
です。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。