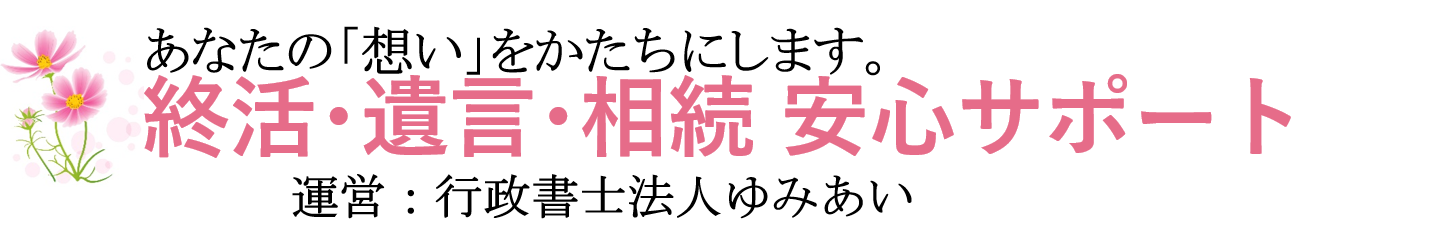自筆証書遺言 筆跡鑑定の信憑性
これは自筆証書遺言が2通あり、「相続争い」が起こり、筆跡鑑定を行ったトラブル事例です。
結論からいうと、筆跡鑑定は鑑定する人(機関)によって結果が異なることもあり万能ではないということです。
2通の遺言書が出てきて裁判沙汰になり争われた事例を
京都の有名老舗かばんメーカー ”一澤帆布 (いちざわはんぷ )”の事件をもとにご説明していきます。
登場人物
一澤信夫氏
一澤帆布工業の三代目社長
遺言書を作成していました。

一澤信太郎氏(長男)
東海銀行に勤める。
2通目の遺言書を持ちだす。

一澤信三郎氏(三男)
一澤帆布四代目社長

一澤恵美氏(三男三郎氏の妻)
1通目の遺言により夫婦で一澤帆布の株を相続する。
一澤喜久夫氏(四男)
先代のもとで一澤帆布の商品を作り続け、技術力は兄弟随一。受賞歴も多数あり。

状況
当時の状況は、三代目一澤信夫氏は事業承継のため1983年には社長を辞任しており、四代目として三男の三郎氏が社長として経営に携わっておりました。


それから、、、
2001年3月
一澤帆布工業の先代社長一澤信夫氏がご逝去されました。
そして顧問弁護士に預けられていた遺言書が開封されました。

内容は、
・長男信太郎氏に銀行預金等の資産を相続させる。
・三男の信三郎夫妻に一澤帆布工業の発行済み株式の67%を相続させる。
・四男喜久夫氏に一澤帆布工業の発行済み株式の33%を相続させる。
というものでした。
この遺言により三男信三郎氏と四男喜久夫氏が経営権を取得し、従前どおり一澤帆布工業は経営を続けていました。


それから、、、
2001年7月に長男信太郎氏が2通目の遺言書があると主張。
1通目の遺言書開封4ヵ月後のことです。
その内容は
・長男信太郎氏と四男喜久男氏が62%の株式を取得する。
・三男信三郎氏は今後一切経営に関わらず、長男である自分が経営権を相続する。
というものでした。
第一の遺言は1997年12月作成
第二の遺言は2000年3月作成
遺言書が2通ある場合、法的には後の日付の遺言書が有効となります。(内容が抵触している部分に関して)
第二の遺言の捏造疑惑
・作成当時一澤信夫氏は脳梗塞を患っており、遺言能力、判断能力があったか疑わしい
・使用されている印鑑が一澤信夫氏が普段使用していなかった「一沢」を用いている
・顧問弁護士がいるのに預託されていなかった
これらの理由におより第二の遺言は捏造ではないかと疑惑が持ち上がりました。
敗訴
そして一澤信三郎氏は第二の遺言は無効であるとして裁判所に訴えを提起します。

しかし、「第二の遺言状を偽物と断定するには証拠不足」ということでまさかの敗訴。

よって第二の遺言の効力により信三郎氏は会社を追い出されました。
それから信三郎氏は新しく「一澤信三郎帆布」を設立しました。

一澤信三郎帆布は、一澤帆布と通りを挟んでほぼ向かい側に店舗を構え営業を行っていました。

当時一澤帆布で働いていた職人は突然現れて経営権を奪い取った信太郎氏のやり方に反発しました。
そして全員が信三郎氏の新会社に移りました。
それからというもの熟練した職人を失い、取引先からも信用を失った信太郎氏による経営は暗礁に乗り上げました。
2006年3月再訴訟
三男信三郎氏の妻恵美氏が原告となり再度「2通目の遺言は無効であると」京都地裁へ訴訟を提起しました。
一澤恵美氏は第一の遺言で夫三郎氏とともに株式を遺贈されることになっていたため、提訴する権利がありました。
結果は
地裁 敗訴
2008年11月大阪高裁 勝訴

2009年6月には最高裁判所も「第二の遺言は偽物である」と認定しました。
逆転劇が起こりました!!
それから2009年にはようやく信三郎氏は一澤帆布の経営に戻ることができました。
なぜ
一回目の訴訟では2通目の遺言は有効とされ、長男が勝訴。
二回目の訴訟では2通目の遺言は捏造とされ、三男(妻)が勝訴。
となったのか。
これは筆跡鑑定の内容(方法)が大きくかかわっています。
鑑定人
長男側 科捜研OBの三人の鑑定人
三男側 神戸大学院の魚住教授や医者など門外漢が三人
魚住教授による解析
これまで裁判で提出されてきた筆跡鑑定は、依頼者の側に立って裁判を有利に導くために鑑定を行ってきた。
しかし、裁判で証拠として採用される以上、科学的かつ、客観性が必要である。
今回の大阪高裁の判決はそのことを認める判決でした。

さて、大阪高裁では、具体的に、どのような点で警察OB鑑定書が否定されたのでしょうか。
主なポイントは3つあります。
ポイント①
「下」の文字
警察OBは、父親の文字は第3点画が第2画から離れていると主張しました。
魚住教授側は、「離れるものもあるが付いているのもほぼ同数ある」と反論しました。
判決では、警察OB鑑定人が、不利な文字を恣意的に取り上げていないと指摘しました。
ポイント②
四男「喜久郎」の「喜」の文字
父親の2通の遺言書には、2通りの字形がありました。
上の部分が「士」となるものと「土」となるものです。
魚住教授は「一般に『士』と書く人が多いが、書道の素養のある方の中には全体のバランスから意図的に『土』と書く人がいて、一澤信夫氏はそのタイプである」と主張しました。
裁判所はこの主張も支持し、警察OBの鑑定書でこの文字を取り上げていないのは恣意的に排除したものと言及しました。
ポイント③
「一澤帆布」の「布」の文字
最初の遺言書では、筆順が「ノ」から始まり2画で「一」を書いています。
後の遺言書では、最初に「一」を書き、つぎに「ノ」を書いています。
これも魚住教授側の主張が認められました。
さて、この内容を目にした時、私が一番最初に感じたことは、一澤信夫氏は遺言を残す時、このように争いになるかもしれない内容の場合自筆証書遺言ではなく公正証書遺言で残しておいた方がよかったのではないかということです。
もしかすると骨肉の相続争いを防げたかも知れません。
自筆証書遺言は
・本当に本人によって書かれたものなのか
・本人の真意によるものなのか(遺言能力があったか)
・不備により要件を満たさない
などで裁判沙汰になることがあります。
公正証書遺言は公証人と証人二人立会のもので作成されている為、確実性・執行力が高いです。
遺された人同士で相続争いになりそうな場合、「不要な相続争い」を避けるために公正証書遺言を検討するのも一つの手段ではないでしょうか。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。