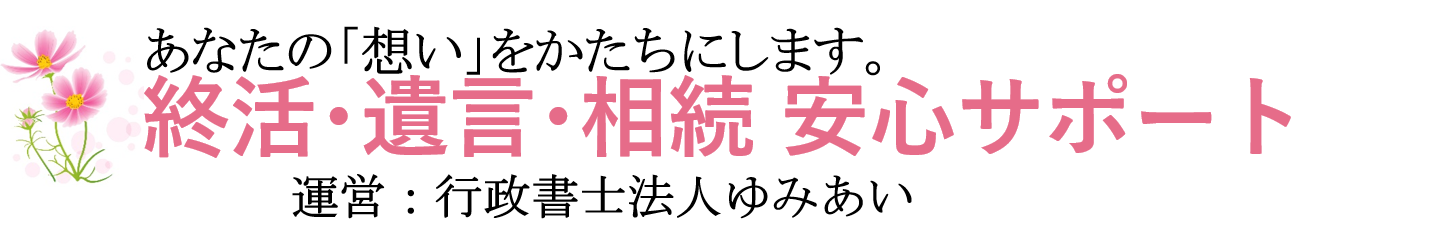[体験談]自筆証書遺言 法務局保管制度を利用しました!

自筆証書遺言をご自宅で保管していた場合、
・紛失
・改ざん
・隠ぺい
・発見されない
などのリスクがありました。
そのため、自筆証遺言を法務局で預かってもらえるサービスがスタートしました。(2020年7月より)
遺言者の住所地もしくは本籍地、または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局に保管申請をすることができます。
その制度を利用しましたので順にお伝えしていきます。
必要書類
用意する書類は次の5点です。
(1)自筆証書遺言
(2)財産目録
(3)申請書
(4)本人確認書類
(5)住民票
1.自筆証書遺言を作成する
自筆証書遺言を作成しましょう。
【絶対的記載事項】
自筆証書遺言の形式は法律で定められています。
「日付・署名・押印」を忘れないようにしましょう。
【加除・訂正】
内容を後で書き加えたり、訂正する場合も決められた形式で行なわないといけませんので注意しましょう。
自筆証書遺言の加除・訂正方法はこちら→
相続人に対しては、 「相続させる」 相続人以外に対しては 「遺贈する」 と記載します。
遺言書に書いて効力が発生するのは、
・財産に関すること
・身分に関すること(相続人廃除や認知) です。
状況によっては「遺留分(いりゅうぶん)」に注意しましょう。
また遺言書に書いて効力のあるものではないけれども「兄弟で仲良く助け合ってこれからも頑張って下さい」など「付言(ふげん)」を残すことも大切です。
【用紙】
法務局で保管する遺言書用紙は「A4」でと決まっています。
これは法務局で遺言書をスキャンして電子データで保管する為です。(ご自宅で保管される場合は用紙の定めはありません) 素敵な便箋を探したのですが、A4サイズのものは中々売っていないんですね。
なのでワードで下記のように印刷して用意しました。

2.財産目録を作成する
財産目録を準備します。
不動産の場合は登記事項証明書のコピー、預貯金の場合は通帳のコピーでも大丈夫です。

法務局で保管する場合の財産目録に関しては必要な余白が決められています。

※参照:法務局HPより
また、すべてのページに「自署・押印」が必要なため、私は登記事項証明書をA4サイズの用紙に85%で縮小してコピーしました。
自筆証書遺言の場合、財産は遺言書内に必ず書かないといけないという決まりはありませんが、正しく書かないと無効になってしまう場合もあるのでできるだけコピーで用意した方が安心ですね。
あとは全ての財産目録に通し番号を記載します。
3.申請書
法務局で遺言書を保管してもらう為の申請書を作成します。
この申請書は法務局のホームページからダウンロートすることができます。
また最寄りの遺言書保管所の法務局でもらうこともできます。

申請書ををダウンロードしてコンビニ等のコピー機で印刷する場合、その機器によっては印刷内容がはみださないように自動的に余白5ミリ分ぐらい縮小して印刷されるものがあります。
この申請書の中にはあらかじめQRコードが印刷されており、このQRコードで保管の管理がされているのでそれが縮小されると正しく読み込めない可能性があります。
ご家庭にプリンターがなくご不安な場合は法務局で申請書をもらって書いた方が安心ですね。
申請書は数枚にわたりますが、書く内容はそれほど難しくないので当日窓口に行って書くこともできるかと思います。
ただし予約時間に全ての書類を揃えて窓口に行く必要があるので必ず予約時間前、余裕をもって法務局へ行く方がいいでしょう。
4.本人確認書類
法務局で保管申請するための本人確認書類は、
・マイナンバーカード
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・乗員手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
いづれか1点ご準備下さい。
保管の申請をする当日、窓口の担当者に提示し本人確認が行われます。
5.住民票
本籍の記載のある住民票の写し等(3ヶ月以内のもの)となっています。

6.遺言書保管所を検索する
自筆証書遺言の保管ができる法務局は決まっています。
住所地により管轄が決まっていますのでどこが自分の管轄法務局か調べます。
私は今回大阪法務局(本局)での保管だったのでそこで予約受付をします。
7.予約する
予約に関しては、
・ホームページからの予約
・電話による予約 があります。
私は今回ホームページで予約することにしました。
まず、法務局のホームページで
(1) ホームページにおける予約(24時間365日) (https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/)
をクリックします。
次に、該当する法務局を選択します。
すると「予約手続き」という画面になるので「大阪法務局遺言書保管手続予約」をクリックします。
そこから予約する日と時間を選択します。
大阪法務局では予約時間は1時間ごとになってましたが、他の法務局を見てみると1時間半のところもありました。
その後、必要情報を入力していきます。
登録が終わると登録完了のメールが届きました。
また予約日が近づくと、そのお知らせメールが届きました。
8.法務局に行く
当日まず法務局で所定の手数料分の印紙(3,900円分)を購入します。
申請書の一番後ろに貼るページがあるのですがまだ貼らないでおいた方が良いです。
窓口担当者に申請書を確認してもらってから貼り付けします。
そして窓口担当者と必要書類の確認をします。
書類の確認にかかった時間はおよそ10分ほどでした。
そのあと担当者より入力作業に30分ぐらいかかるのでお待ちくださいとご案内を受けました。
結構かかるんですね。
そして遺言書保管の控えをもらい完了です!
法務局における遺言書保管制度を利用してみた率直な感想は予約が必要だったり様式も厳格に決まっていて少し手間はかかると思いました。
けれどもとってもいいメリットもありました!
それは遺言者の死後、指定した人に遺言書が法務局に保管されているということの通知がいくというものです。
これは保管申請書の中に指定するところがあるり、
・財産を受け取る人
もしくは
・遺言執行者
から選べます。
公証役場にて作成する公正証書遺言にはこのようなサービスがないので利便性に優れとってもいい仕組みだと感じました。
安全に保管できることや相続人等に通知がいくのはすごくメリットがあるので今後は利用される方が増えるかもしれませんね。
最後に、自分で遺言書を作成する場合、法務局ではその内容の有効性まで見てくれないのでご不安な方は専門家に相談をして頂くか公正証書遺言で作成される方が安心ですね。
少しでも費用を安くまた、内容を誰にも知られたくないなどで自筆証書遺言を作成する場合は是非利用したい制度ですね。
ご自宅でスマホ・パソコンからWeb面談可 詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい
LINEでお問い合わせはこちら