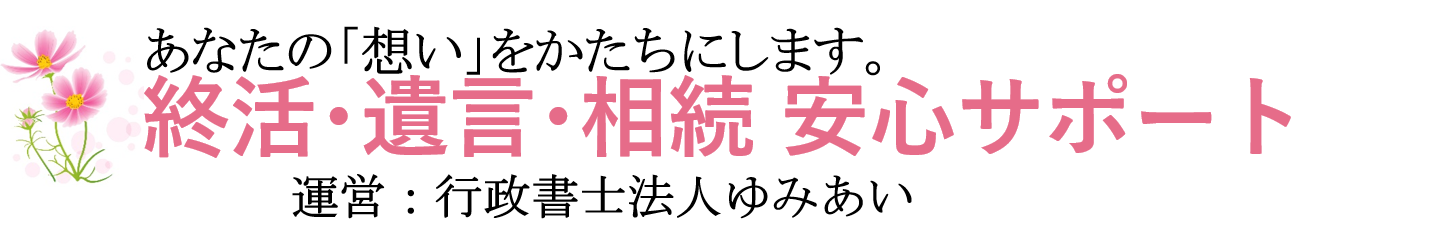遺言書費用・相場・手続きの流れ|【大阪】Lien行政書士法務事務所
ここでは、
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」について
・自分で作成する場合
・専門家のサポートを受け作成する場合
それぞれの、
①費用 ②必要書類 ③手続きの流れについて、お伝えしていきます。

自筆証書遺言作成の費用・必要書類・手続きの流れ
費用
ご自身で作成する場合
ご自身で作成される場合、遺言書作成としての費用は0円です。
しかし、もし相続人以外の人に財産を譲る場合や、どこかに寄付を検討している場合は正確な情報を得るため戸籍謄本や登記簿謄本の取得が必要になるケースがあります。
役所等に支払う手数料は一般的には400円~600円ぐらいになります。
大阪市
戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本) 450円/1通
除籍謄本・改製原戸籍謄本 750円750/1通
戸籍謄本は郵送でも行うことができます。
その時は手数料分の定額小為替を同封します。
また遺言書をご自宅で保管すると、紛失や改ざん、また発見されないなどのリスクがあります。
これらの対策として法務局による自筆証書遺言保管制度を利用するのもいいでしょう。
保管制度を利用する場合の法務局への手数料は3,900円になります。
専門家のサポートを受け作成する場合
専門家のサポートを受け作成する場合は内容ごとに○○円、またはパック料金で○○円となっているケースが多いです。
内容ごとに料金が設定されているとは、
・相続調査 3万円~
・相続財産調査 3万円~
・遺言書起案 3万円~
・遺言執行 相続財産の1~3%
・遺言書保管料
などです。
全てセットになったもので、大体8万~10万くらいが相場となっていますが、財産額により設定しているところが多いです。相続財産の○%などですね。当事務所では
またご自身で作成する場合も、戸籍など役所への手数料がかかりますが、専門家のサポートを受け作成する場合も報酬+役所などへの手数料実費も必要となります。
必要書類
ご自身で作成する場合
財産目録を添付する場合、
・不動産の登記簿謄本
・預貯金通帳のコピー
などが必要となります。
不動産は土地と家屋と登記が分かれているため、ご自宅を相続させたい場合など土地と家屋のそれぞれの不動産情報が必要となります。
また投資信託や株式など、どの相続財産も「特定できるもの」が必要となります。
また相続人らの戸籍謄本や遺言者の出生~現在の戸籍謄本も、相続手続きで結局必要になりますので、取得しておくと相続人の負担を減らすことができます。
遺言書作成時に取得しておくと、それだけ正確な情報をもとに遺言書を作成することもできますからね。
専門家のサポートを受け作成する場合
専門家のサポートを受け作成する場合も、相続人を特定するために戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍などが必要になります。
また相続財産の情報として預貯金の情報がわかるもの(預金通帳)や不動産の登記簿謄本、株券、相続財産がどんなものであるのか「特定するための」情報となり資料が必要です。
手続きの流れ
ご自身で作成する場合
①必要な情報を取集する
→相続人を確定して、相続財産を精査する
②内容を検討する
→①の相続人調査や相続財産調査の結果をもとに遺言の内容を検討します。この時遺留分や遺言執行者に注意して作成することが望ましいです。
③遺言書を書く
→自筆証書遺言は自筆で手書きで書く必要があります。財産目得は預貯金通帳などのコピーの添付でも可能となっています。財産目録を添付する場合はその目録ごとに署名や捺印が必要になります。
④遺言書の保管について考える
→ご自宅で保管する場合、発見されなかったり紛失してしまうと意味がありません。保管場所については慎重に検討しましょう。
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度もあります。それを利用するのもいいでしょう。(手数料3,900円)
専門家のサポートを受け作成する場合
自筆証書遺言作成で具体的に内容を検討するために戸籍の調査や財産の調査が必要になりましたよね。
ここでは自筆証書遺言作成で専門家によるサポートを受ける場合、
①法的に有効な形で作成するためのアドバイス
②事後のトラブルを回避するためのアドバイス
③相続人調査
④相続財産調査
をするためにもやはりご自身で作成する場合の流れと同様に相続人の調査や相続財産調査を行います。
戸籍の調査や相続財産の調査では専門的な知識を要するものも多く、専門家に依頼するとこれらの煩雑な手続きを行ってくれるのでご自身は専門家から聞く内容をもとに遺言の内容を検討するという流れになります。
自筆証書遺言とは全文を自筆で、手書きで書く遺言書のことです。
2019年の相続法改正により財産目録に関しては不動産の登記簿謄本や預貯金の通帳のコピーの添付でも可能となりました。
財産目録を添付するときはいくつかルールがありますので詳しくは下記をご確認下さい。
→【相続法改正!】自筆証書遺言 / 財産目録が変わりました!
それから自筆証書遺言はその作成にもルールがあります。
詳しくはこちらをご確認下さい。
→自筆証書遺言の加除・削除・訂正の方法は法律で決められています!
ご自身で書籍などを参考に作成することもできますが、遺言はただ単に「○○を相続させる」と書くだけでは不十分なケースもあります。
「遺留分」や「寄与分」「生前贈与」「遺言執行者」に注意して作成するようにしましょう。
ご自身で作成される場合、後の紛争リスクや内容が不十分なことにより起こるトラブルなどきちんと理解した上で作成するようにしましょう。もちろん内容も書き方もきちんとしたもので、その実現が不可解なものでなければ法的有効なかたちの遺言書をご自身で作成することも可能です。

公正証書遺言作成の費用と必要書類・手続きの流れ

公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言書のことで、公証役場は全国におよそ300ヶ所あります。
公正証書遺言は公証人や立会人とともに作成する遺言で自筆証書遺言に比べ「執行力」や「証明力」があります。
自筆証書遺言は紛失や改ざん、そもそも発見されないなどのリスクがあります。しかし公正証書遺言は公証役場で遺言書を保管してくれるので紛失、改ざんなどのリスクもなく安心です。
費用
ご自身で作成する場合
ご自身で公証役場へ出向き作成する場合、
①戸籍など取得費用
②公証役場への手数料
③立会人を依頼する場合の費用
が必要となります。
①戸籍など取得費用
公証役場へ提出する必要書類に戸籍謄本や不動産の登記簿謄本や納税通知書、印鑑証明書などががあります。
それぞれの役所や法務局等への手数料が必要になります。
必要な書類は作成する遺言の内容により異なります。
手数料はお住まいの市区町村により多少異なりますが、戸籍謄本450~650円、不動産登記簿謄本600円、印鑑証明書400円前後が必要になります。
不動産登記簿謄本は土地、家屋それぞれ不動産の件数ごとに必要となります。
②公証役場への手数料
公証役場へ支払う手数料が必要になります。これらの手数料は財産額や遺言の内容により異なりますが、公証役場から事前に見積りをもらうことができます。一般的な内容であれば3万~8万円ぐらいの範囲になると思います。
公証役場への手数料は政府が定めた「公証人手数料令」(平成5年政令第224号)という政令により定められています。

③立会人への費用
公正証書遺言作成には立会人が2名必要になります。
ご自身でお知り合いの方などにお願いすることもできますが、相続人やその遺言に利害関係のある人は立会人になることができません。
公証役場等へ立会人を依頼する場合、1人あたり日当として6,000~10,000円必要となります。
専門家のサポートを受け作成する場合
公正証書遺言作成のサポートをしている専門家には弁護士、税理士、司法書士、行政書士などがあります。
一部金融機関でも遺言書作成支援をしているところがありますが、弁護士などと提携しているところがほとんどです。
費用は事務所により異なりますが、弁護士、税理士、司法書士、行政書士の順に高い傾向があります。
遺言により紛争が発生しそうならその後の対応も含めて弁護士、また資産が多く具体的に相続税対策も合わせて検討したい場合は税理士、できれば安く専門家のサポートを受け作成したい場合は司法書士や行政書士にお願いするなど検討してもよいでしょう。
いずれにせよ専門家に依頼をする場合は、遺言相続業務に特化した事務所を選ぶことをおすすめします。
税理士でも税のことしかわからない、行政書士でも許認可のことしかわからない事務所もあります。
最適なサポートを受けるためにも遺言相続業務を専門的に行っているところを選ぶようにしましょう。
また一度無料相談などを利用して話しやすい先生か、コミュニケーションがうまくとれる先生なのか確認しましょう。
遺言書作成は非常に繊細なことなのでご自身の想いを十分汲み取って検討、アドバイスしてくれる話しやすい事務所を選ぶことをおすすめします。
専門家費用相場
弁護士費用 10~50万円前後
税理士費用 10~50万円前後
司法書士費用 10~20万円前後
行政書士費用 10~20万円前後
必要書類
ご自身で作成する場合
遺言の内容に応じて
・戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・固定資産税納税通知書
・預貯金通帳
・本人確認書類
・印鑑証明書
などが必要となります。
また実印や認印などの印鑑も必要となります。
専門家のサポートを受け作成する場合
ご自身で作成する場合の必要書類取得を専門家が代わりに行ってくれます。
手続きの流れ
ご自身で作成する場合
必要な書類を揃えて最寄りの公証役場へ行きます。
必要な書類は事前に公証役場へ確認するようにし、また公証人との面談は事前にアポととるようにしましょう。
遺言の内容が固まれば、後日立会人同席の上改めて公正証書遺言を作成します。
公証役場へ出向くのが難しければ、自宅など指定の場所へ公証人に来てもらうこともできます。
その時は別途公証人への出張手当が必要となります。
専門家のサポートを受け作成する場合
専門家が必要な書類を取得し、公証人と打ち合わせをし文案を作成します。
そして専門家が公正証書遺言作成の日程調整、立会人への就任などを行います。
それぞれのメリット・デメリット
遺言書をご自身で作成する場合はなんといっても費用が抑えれるメリットがあります。
しかし遺言書は決められた形式で作成する必要があり、不備により無効となってしまうこともあります。
また内容が十分でなく残された人が困ったり紛争になりそうな内容になってしまうことがあります。
専門家に依頼すると、最低でも10万円くらいの費用はかかりますが、せっかく作成するのであればきちんとした遺言書を作成した方がいいですよね。
何のために遺言書を作成するのかをもう一度しっかり考え、どういう方式の遺言にするのか、自分で作成するのか専門家のサポートを受け作成するのか選ぶようにしましょう。
遺言の内容を実現する遺言執行者とは
遺言書は書いただけでは終わりではありません。
ご逝去後、相続人らはその遺言書をもとに相続手続きを行います。
その時、遺言書に遺言執行者を定めていないと、書いていないと、その遺言の内容の実現が困難となるケースがあるので注意が必要です。
できるだけ手続きを適切に行えそうな人がいれば、できればその人に事前に了承を得た上で、遺言執行者を定めておくことが望ましいです。
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
大阪府大阪市〇〇〇〇 長男 鈴木 一男
遺言書に記載のない財産が出てきたら?
遺言書に記載のない財産が出てきた場合、通常の遺言書がない場合の相続手続きと同様相続人全員で「遺産分割協議」が必要になります。
遺産分割協議は状況によってはその話し合いをするのが難しく困難を伴うものもあります。
将来起こりうるリスクをできるだけなくすため、遺言書作成時に財産に漏れがないように「その他の財産全てを○○に相続させる」という文言も記載することも可能ですが、その他の財産全てと記載すると借金などのマイナス財産も相続するので注意が必要です。
遺言書を作成する場合は内容をよく検討し、きちんとした遺言書を作成されたい場合一度専門家に相談するようにしましょう。

遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。