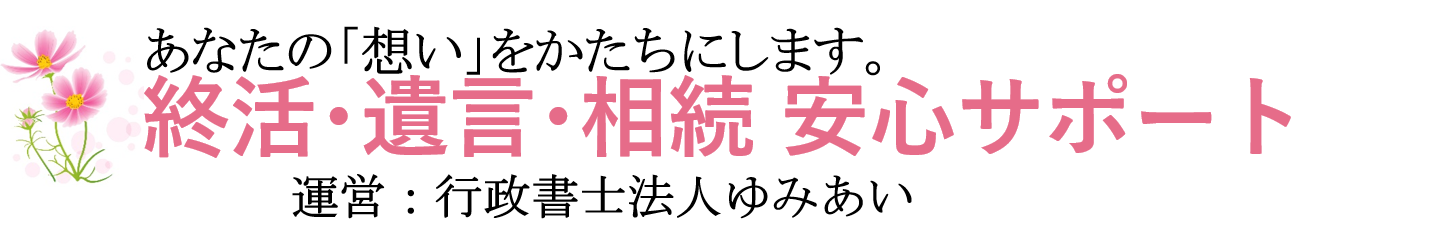未成年後見人 遺言書の書き方~大切なこどものために遺言で備える
先日とある女性の方から自分が亡くなった後残された子供たちのことが心配なのできちんと対策をしておきたいと相談を受けました。

その女性は今のご主人とは再婚であり、前の夫との間にできた2人の子どもを連れての再婚でした。
しかし2番目の夫はあまり素行がよくなく、自分が亡くなった後幼い子供たちがどうなるのか心配とのことでした。
ここではご自身が亡くなった後、子供たちの保護者となる「未成年後見人」についてご説明をしていきます。
親権者
夫婦が婚姻し、子供を授かると共同親権というかたちで父・母どちらも親権者となります。

親権者とは、
・未成年の子を養育監護し、
・その財産を管理し、
・子を代理して法律行為をする
権利・義務を有する者のことです。
しかし、離婚すると父・母どちらか一方のみが親権者となります。
そして、たとえば母が子供の親権者となったが、病気などで亡くなってしまった場合、その子供には保護者となる親権者がいない状態になります。

このようなケースでは親族などが家庭裁判所に親権者の変わりとなる「未成年後見人」の申立てを行います。
そして親権者となっている自分に万が一のことがあり、我が子のことが心配な時「遺言書」で子供の保護者となる「未成年後見人」を指定しておくことができます。
親権者の遺言によって未成年後見人または未成年後見監督人に指定された者は、遺言者の死亡と同時に未成年後見人または未成年後見監督人に就任します。
遺言書で未成年後見人を指定する
遺言書で未成年後見人を指定する場合、その指定する後見人の
・名前
・生年月日
・住所
の記載をします。
遺言者は、未成年者である長男鈴木一男(令和〇年〇月〇日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。
氏 名 未成年後見人の氏名
生年月日 未成年後見人の生年月日
住 所 未成年後見人の住所
そして、報酬を定める場合、その額と、未成年後見監督人を指定する場合、その者の氏名等も記載します。
未成年後見人に指定された者は遺言者の死亡後10日以内に未成年者の在する市区町村役場に届けます。
その時未成年後見人届や戸籍謄本、遺言書を提出します。
この届出が10日と決められていることから「公正証書遺言」で作成するのが望ましいでしょう。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があり、手続きに1ヵ月ほど時間かかります。
また自筆証書遺言の法務局での保管では検認は不要ですが、遺言書を受け取る手続きに予約が必要だったりするので公正証書遺言で作成しておく方が安心です。
公正証書遺言の場合、遺言書作成時に正本や謄本を受け取ることができます。
また遺言書作成時には遺言書の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておいた方がいいでしょう。
遺言執行者を定めておくと遺言書に書かれている内容の実現をスムーズに行うことができます。
ただし、遺言の内容によっては手続きに専門の知識を要するため専門家を指定しておいたほうがよいケースもあります。

再婚相手と養子縁組をしている時
母が離婚したあと別の方と再婚し、その再婚相手とお子さんが養子縁組をしている場合は「共同親権」という状態になり、法律上「最後に親権を持つ者は…」に当てはまらない可能性があります。
しかしそれだけをもって遺言書自体が無効となるかの判断は難しく、再婚相手がその未成年後見人の指定に同意している場合有効となる余地もあります。

家庭裁判所に未成年後見人の申立をする
申立できる人
・未成年者(申立能力を有する者)
・未成年者の親族
・その他の利害関係人
申立に必要な費用
収入印紙800円分(未成年者一人につき)
申立に必要な書類
・申立書
・未成年者の戸籍謄本/住民票または戸籍の附票
・未成年後見人候補者の戸籍謄本
・親権者がいないことを証する書面(死亡の記載された戸籍謄本など)
・未成年者の財産に関する資料

遺言書で指定する場合と家庭裁判所に申立する場合の共通事項
未成年後見人になれる人
「未成年後見人になれない人」が法律で定義されています。
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
・破産者で復権していない者
・未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)
・行方の知れない者
はなることができません。
未成年後見人の報酬
遺言書により報酬を定めることができます。
また無しとすることもできます。
家庭裁判所より報酬額の指定があった場合支払わなければなりません。
未成年後見監督人
未成年後見監督人とは未成年後見人の職務を監督する人のことです。
未成年後見人が未成年者の養育看護や財産管理をきちんとしているか心配な時、未成年後見監督人を遺言により指定しておくことができます。
遺言者は、未成年者である長男鈴木一男(令和〇年〇月〇日生)の未成年後見監督人として、次の者を指定する。
氏 名 未成年後見監督人の氏名
生年月日 未成年後見監督人の生年月日
住 所 未成年後見監督人の住所
まとめ
親権者がいない、またはいなくなった時に備え「未成年後見人」について知り、対策しておくと安心ですね。
その方の状況によりいろいろ検討することもあると思いますので、一度専門家などにご相談される方が安心ではないでしょうか。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。