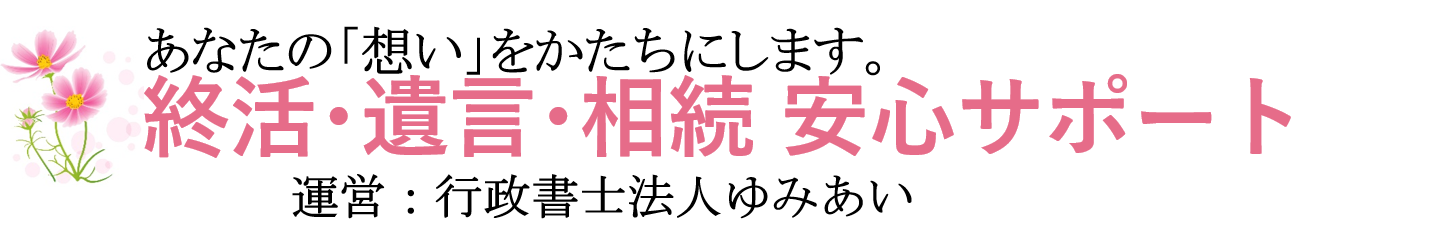【相続法改正!】配偶者の住まいを確保/配偶者居住権の創設

配偶者居住権とは
夫婦がのどちらか一方がなくなると相続が発生します。 相続が発生し、遺言がなく、相続人同士が不仲で遺産分割協議がまとまらない場合、残された配偶者と子供などで分配します。 しかし遺産の大部分を占めるのが不動産しかく、そのため法定相続通りに分配すると残された配偶者は長年住み続けていた自宅に住めなくなってしまうということもあります。 高齢の配偶者にとっては残された人生を住み慣れた自宅で過ごせなくなることはとても辛いですよね。
そこで配偶者の暮らし・住まいを保護するために「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者がその家に住み続けられる「権利」の取得です。
制度の趣旨としては残された配偶者の住まい・暮らしを保護する目的です。

例えば、5,000万円の自宅と3,000万円の預金を持った太郎さんという人がいました。
太郎さんには妻花子と、一人息子に一郎さんがいました。
しかし一郎さんは生前ご両親と不仲になり家出をしていました。
そして太郎さんが亡くなってしまいました。
相続財産は5,000万の不動産と預貯金3,000万の計8,000万円。
妻花子さんと息子一郎さんの法定相続分は1/2ずつ。
金額に換算すると4,000万ずつです。

太郎さんの妻花子さんは高齢なこともあり、住み慣れた家で余生を過ごしたいと考えています。
もし花子さんが家を相続するとなると息子一郎さんにその差額分1,000万を払う必要があり、また花子さんは預金を相続できないので現金を所有することなく不安な余生を過ごさなければなりません。
そこで新しく創設されたのが「配偶者居住権」です。
これは居住建物を「所有権」と「居住権」に分けることができる制度になります。
配偶者にその建物に住み続ける権利を与え、息子にその建物の所有権を与えるというものです。