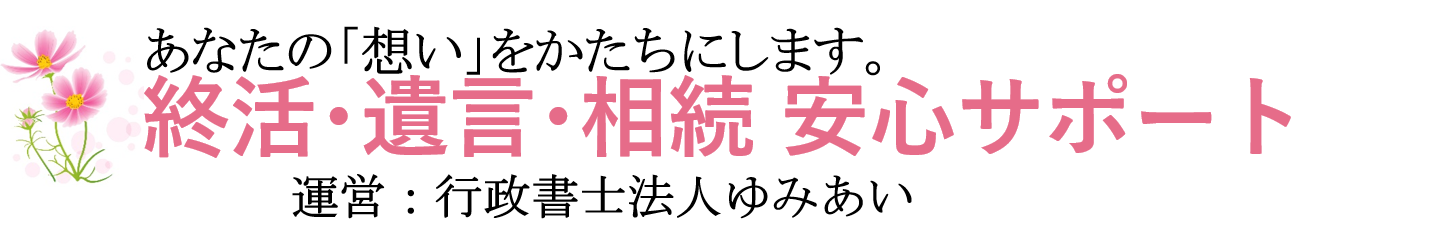公正証書遺言の作成方法と選ぶメリット
公正証書遺言とは 「遺言書 」を 「公正証書」で作成することです。
公正証書って何?
どうやって作るの?
そう思われる方もたくさんいらっしゃいますよね。
ここではまず公正証書遺言について簡単にわかりやすくご説明します。
1.公正証書とは

公正証書とは公証役場にて公証人によって作成される公文書です。
日本公証人連合会によると公証役場は全国におよそ300カ所あり、そこで働く公証人と呼ばれる人たちはおよそ500名います。
その公証人は高度な法律専門知識を持っており、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな人が勤めています。
その公証人によって公証役場で作成される書類は「公文書」として「証明力」や「執行力」を有している為、遺言書や離婚協議書など幅広く利用されています。

2.公正証書遺言の作成方法

公証役場は、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与などを行う認証機関です。
そのため遺言書作成に必要なことを1から10まで行ってくれるわけではありません。
認証するための機関ですからね。
また公証人(公証役場で働く人)自体が遺言書を起案する立場でもありません。
もちろん簡単な相談には応じてくれるとは思いますが、公証役場で働いている公証人は元検察官や元裁判官が多く、家庭裁判所で相続関連の事件を扱っていたかどうかはわかりません。
よって遺言書作成に必要な法律の知識を備えているかはその人次第です。
そこで遺言書作成をサポートしている士業などまずは専門家に相談し、専門家を通じて公証役場で公正証書遺言を作成することをおすすめします。
なお、公証役場で求められる必要書類は以下のような内容になります。
当事務所での公正証書遺言作成の流れ
1.遺言者から相続人関係、遺産の内容、遺言者の希望を聞き取り、遺言書案を作成します。
合わせて必要な戸籍謄本やと不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書などを取得します。2.遺言書案がまとまれば、必要書類とともに公証人に送って意見を求めます。
3.公証人と日程調整をし、遺言書作成日を決めます。
4.遺言書作成日に遺言者、証人とともに公証役場へ出向きます。
5.公証役場で本人確認等を行い、遺言書を作成、署名、捺印します。
この時公証役場への手数料をお支払いします。
公正証書遺言を作成する時に証人2名立会いが必要です。
証人は誰でもなれるというわけではなく、以下「なれない人」が法律で定義されています。
・未成年者
・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
この時、公証人手数料令という法律で定められた手数料を公証役場に支払います。
この手数料は財産額、財産を残したい人の人数などによって変わりますが、打ち合わせの段階でお願いすれば事前に見積り額を提示してもらえます。
手数料 ↓ 日本公証人連合会より
10 手数料 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
公正証書にすると「原本」「正本」「謄本」などが作成されますが、遺言の内容に応じて必要な人が保管します。
3. 公正証書遺言の作成数
日本公証人連合会の統計データによると公正証書の作成数は10年前よりは少し増加してまずが、ここ最近は横ばいに推移しております。
| 暦年 | 遺言公正証書作成件数 |
|---|---|
| 平成22年 | 81,984件 |
| 平成23年 | 78,754件 |
| 平成24年 | 88,156件 |
| 平成25年 | 96,020件 |
| 平成26年 | 104,490件 |
| 平成27年 | 110,778件 |
| 平成28年 | 105,350件 |
| 平成29年 | 110,191件 |
| 平成30年 | 110,471件 |
| 令和元年(平成31年) | 113,137件 |
4.公正証書遺言の必要性

例えば遺言書を自分で手書きで作成し、自筆証書遺言で作成したとき、場合によってはその遺言書が本当に本人によって書かれたものなのか、という争いになることがあります。
自筆証書遺言の場合、争いになり裁判にまで発展すれば筆跡鑑定が行われたり様々な調査がおこなわれることが予想されますが,これを公正証書にしておくと公証役場で本人確認もきちんと行われており、本人が作成したとの「証明力」にもなります。
また公文書としてその内容を実現するための強力な「執行力」にもなります。
遺言書を自筆でご自分で作成する場合、きちんと正しい方法で作成しなければ不備などにより無効となることもあります。
せっかく書いた遺言が、その「想い」が実現されないなんてことがおこらないよう、当事務所では公正証書遺言で作成することをおすすめしています。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。