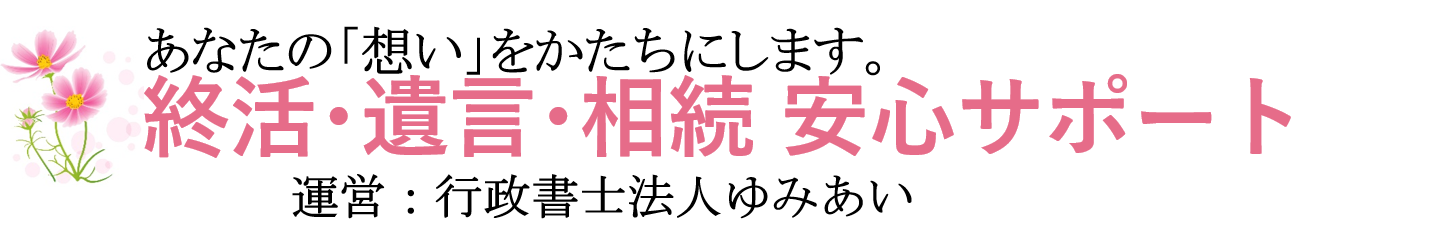認知症と診断ー遺言書は作成できる??作成方法と注意点
親が認知症だと言われたのですが、遺言書は作成できますか?

こういったご相談を頂くことがたくさんあります。
結論からいうと、
それぞれの状況により異なります。
認知症といっても様々な程度があり、直ちに遺言能力を失うわけではありません。
しかし相続開始後に遺言の効力が争われることもあるので、いくつか検討する必要があります。
順にみていきましょう。
1.遺言能力

遺言書は本人の財産について誰に相続・遺贈したいかを意思表示し、それを自分の死後実現するというものです。
なので遺言書を作成する時ご本人様が、
・遺言書を作成する意思
・自分の財産の処分についての明確な意思
・それを表示できる状態
になければなりません。
ご子息が親が
「あなたに全財産をあげると言っていた」
ということでは遺言書を作成することはできず、遺言書作成時、本人が明確に意思能力を有している必要があります。
このことを法律では「遺言能力を有している」といいます。
この遺言能力を有しているかどうかは最終的には裁判所が判断します。
Aさん(85歳)は中等度から高度のアルツハイマー型認知症でした。信託銀行が証人となり銀行が手続きを行い公正証書遺言を作成していました。その内容は「多数の不動産やその他の財産について複数の者に相続させる。遺言執行者について項目ごとに2名に分けて指定し、報酬に関しても細かく比率を分けるなど複雑な内容」のものでした。銀行が作成したものを公証人が読み上げ遺言者Aさんに確認して作成していましたがこの遺言は遺言能力が否定される判決となりました。
重度の認知症にも関わらず細かく内容を指定することはできなかっただろうということです。
2.医師の診断書

「認知症」であるかの医学的判断は医師がします
医師がする認知症の判断はあくまで医学的に心身が認知症の状態にあるというもので、認知症なので遺言書を作成する能力はないというものではありません。
しかしこの診断書も裁判所は遺言能力の有無の判断材料とするのでとても重要なものになります。
3.相続争いになりそうかどうか

認知症の方が遺言書を作成する時に問題となるのが、法定相続人同士の争いです。
例えば法定相続人が長男A、次男Bの二人兄弟だったとします。
長男Aに全財産を相続させるという遺言書があった時、次男Bが「遺言者は遺言書作成時認知症であった為遺言能力を有しておらずこの遺言書は無効である」という訴えを起こす可能性があります。
法定相続人の関係性も考慮し遺言書作成を検討する必要があります。
4.争いになりそうな場合備える
ここで一番大切なのが、相続争いになりそうな場合備えるということです。
1.公正証書で作成する

一般的には遺言書は自筆証書遺言か公正証書遺言で作成される場合がほとんどです。
認知症の可能性がある場合、公正証書遺言で作成するようにしましょう。
公正証書遺言は遺言者から公証人に対して遺言の内容が口授され、証人2名の立会も必要なことから自筆証書遺言より「証明力」や「執行力」が高いといえます。
よって後日遺言書の有効性を争われる可能性が低くなります。
2.遺言書作成時の様子を記録として残しておく

遺言書作成時に遺言者が遺言能力を有していたことを証明できるものを残しておくようにしましょう。
例えば遺言書作成時、その様子を映像に残しておくのもいいでしょう。
またその時「長谷川式簡易知能評価スケール」など認知症の程度を判断するテストをして、記録を残しておくのもいいでしょう。
長谷川式簡易知能評価スケールは30点満点中20点以下で認知症の可能性が高いといわれ、10点以下では高度認知症の可能性が高いと言われています。
また医師による診断書もあればなお良しです。
かかりつけ医に遺言者の様子や言動をカルテに記載してもらうように頼みます。
またかかりつけ医から「遺言書は書けると思いますよ」という言葉があれば、その旨を診断書に記載してもらいます。
お医者さんが「遺言能力はある」と言ったとしても、遺言能力があると確定できるわけではないのですが、重要な証拠となります。
どこでもらえるかわからない場合はネットなどで最寄りの認知症専門医を探すといいでしょう。
認知症の方が遺言書を作成される場合、遺言能力やまわりの人との関係性を考慮して慎重に判断する必要があります。
難しい問題になりますので作成を検討している場合はまず専門家に状況をお話し、相談されといいでしょう。
遺言書に書いて効力があるものは法律で決められています。
しかし法的な効力はなくても遺された方へのメッセージとして遺言書に「想い」を記しておくことはとても大切です。
遺された人たちはどうしてあなたがそのような内容の遺言書を書いたのか理解することができ、あなたの気持ちに寄り添うことでその遺言の内容を受け入れやすくなります。
またあなたの「想い」を知ることで相続人同士の不要な争いを避けることができます。
「死」という悲しい出来事がおきた最中にある相続。